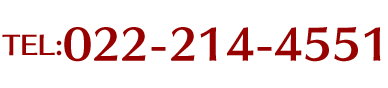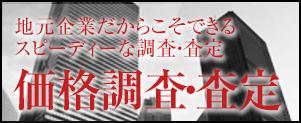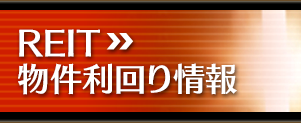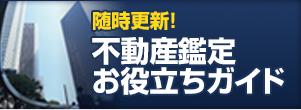【判例】『定期賃貸借契約(定期借家)における期間満了後の使用継続』

期間満了後に建物が継続使用されたケースにおいて、定期建物賃貸借としての効力が否定された裁判例です。
定期建物賃貸借は更新のない賃貸借であり、期間満了により契約は終了します。契約期間が満了しても、その後長期間賃借人が継続して建物を利用し続けるものの、賃貸人が明け渡しを求めることもなく賃料も引き続き支払われているケースがあります。契約は終了するが契約を対抗できないというあいまいな状態が想定されます。このような場合・・
東京地判平成21.3.19では、
「期間満了後、賃貸人から何らの通知ないし異議がないまま、賃借人が建物を長期にわたって使用継続しているような場合には、黙示的に新たな普通建物賃貸借契約が提携されたものと解し・・」と述べられています。
賃借人サイドから言えば、定期借家契約であることを否定して明け渡しを拒否することが可能となるということになります。定期建物賃貸借(定期借家)の終了後に別個の契約成立を認めたはじめての例として注目されています。
170524
(注)本文と表示画像は何ら関連性はありません。
【仙台市のアパート、マンション賃貸事情】 平成25年住宅・土地統計調査より

平成25年住宅・土地統計調査によると、平成25年の宮城県の空家率は9.4%、仙台市は10.0%。山梨県の22.0%が全国で最も高く、宮城県は最も低かったとのことです。
同調査には、借家の1ヶ月当たりの家賃調査もあり、それによると仙台市の1ヶ月の家賃平均は専用住宅で49,248円となっています。5年前の平成20年の調査に比べてマイナス2.6%の下落となっています。震災後の急激な物件不足があっただけに、家賃下落はやや意外な気もします。
一方、民営借家の総数は平成25年で224,800戸、5年間で約20%も増えています。共同住宅は28,300棟で8.4%の増加。震災後の物件不足によって利便性の良好な地域においては強気の賃貸条件がみられましたが、一方で、共同住宅等の貸家が増加したことにより、競争力に劣る物件や地域において大幅な賃料値下げもみられ、全体的に下落傾向を表したようです。
現在、震災被災者のいわゆる「みなし仮設住宅」入居者は、平成28年3月31日時点で仙台市にはまだ6,843人おられます。平成29年3月末に仮設住宅が終了することを考えると、当然ながらこの1年以内で仙台市内のアパート、マンションの空室率の増加が予測され、賃料はやや弱含みで推移すると考えられます。
さらに、震災後続いていた仙台市の人口増加傾向も昨年あたりからペースダウン傾向が顕著になってきました。仙台市の昨年の社会増加数は3,000人を切っています。人口増加傾向もそろそろ終盤に入った模様です。
低金利や金融機関の積極姿勢もあって、個人、法人を問わず収益物件の引き合いは依然として強く、価格の高騰で取引利回りは低下しています。利回りが低下するなか不動産価格はそろそろピークとの見方もあり、最近では出口戦略に舵を切り始めた投資家による売り物件も市場に出回ってきているようです。
160510
「特定空き家」の判断基準

5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家対策特措法)が完全施行されます。空家対策特措法は2014年11月に公布、15年2月26日に一部施行され、「空家」と判断する目安は「建築物がおおむね1年間使われていない」とする基本方針が示されています。
特定空家の判断基準を抜粋すると次の7つが重要となります。
1、建築物の著しい傾斜 (不同沈下、柱の傾斜・・)
2、構造耐力上主要な部分の損傷 (起訴の破損、変形、土台の腐朽、破損・・)
3、屋根、外壁などの脱落・飛散の恐れ (屋根の変形、壁体を貫通する穴・・)
4、擁壁が老朽化し危険となる恐れ (ひび割れの発生・・)
5、ゴミの放置、不法投棄など (臭気の発生があり周辺住民の日常生活に支障を及ぼす・・)
6、周囲の景観と著しく不調和 (多数の窓がらすが割られたまま放置、立木の繁茂)
7、空家に住み着いた動物の問題 (鳴き声の発生や臭気で周辺住民の日常生活に支障を及ぼす・・)
いずれもおおまかな基準であるため自治体(市町村長)の細やかな判断に委ねられることになります。
特定空家に指定されると、所有者が措置を履行しない場合には、市町村長が行政代執行による解体作業などが実施されます。
150521